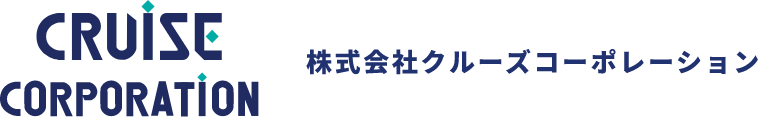不動産投資または収益不動産といえば、年収や利回りなどの収入の部分に目が行きがちですが、収入と同じくらい重要なのがランニングコストです。
不動産投資におけるランニングコストとは収益不動産運用に係る経費のことです。一覧にしてみると以下の項目があります。
・固定資産税
・都市計画税
・所得税・住民税
・PM費(入居者に関する費用)
・BM費(建物に関する費用)
・水道光熱費
・修繕費用
・etc.
上記一覧は大枠であり、細分化すると相当数の項目があります。また、物件によってそれぞれの金額は異なります。
同じ価格、同じ利回りの収益不動産があったとしても、ランニングコストによって、手元に残る手残り額(キャッシュフロー)が高くなったり、低くなったりするのです。
〔例〕
【共通条件】
物件価格:10,000万円
満室年収:1,000万円
表面利回り:10%
【物件Ⓐ】
ランニングコスト:200万円
キャッシュフロー:800万円(実質利回り:8%)
【物件Ⓑ】
ランニングコスト:400万円
キャッシュフロー:600万円(実質利回り:6%)
しかも、このランニングコストはポータルサイト上や、物件資料(マイソク)に記載が無いことが多いです。ですので、物件毎に確認・調査が必要となります。
今回はそんなランニングコストを項目ごとに解説していきます。
(※一棟アパートや一棟マンションを想定しております。貸家や区分マンションにはあてはまらない内容がございます。)
固定資産税・都市計画税
毎年1月1日に不動産を所有している者(個人・法人)に課税される税金です。
それぞれの計算方法は
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%
となります。(※様々な軽減措置がありますが、今回は説明を省きます。)
計算方法から分かるように、計算の基となるのは固定資産税評価額です。「固定資産税評価額は実勢価格の70%」と言われておりますが、収益不動産の場合は当てはまらないことが多いです。
なぜなら、収益不動産の売買価格は利回りから逆算する収益還元法という査定方法を基に決められているからです。
収益不動産以外のマイホーム用地や中古戸建は、原価法という土地価格と建物価格を周辺事例や再調達価格などを基にそれぞれ算定し、合計して算出する手法で査定されており、固定資産税評価額も同様の査定方法が基準となっております。
基になる査定方法が違うため、「固定資産税評価額は実勢価格の70%」が当てはまらず、同じ10,000万円の収益不動産なのに、片方は固定資産税50万円、もう片方は固定資産税150万円なんてこともあるのです。
□CheckPoint
固定資産税が高い=悪い物件とは限りません。「固定資産税が高い=固定資産税評価(実勢価格の70%)が高い」ので、原価法による査定価格が高いということになります。金融機関が物件査定を行う際には、この原価法による査定価格(積算価格)を重視することが多いです。つまり、固定資産税が高い物件は、金融機関の評価が高い物件であり、金利などの条件が有利になる傾向が高いです。
金利や返済年数の条件が良ければ、固定資産税が少し高くても、手残り額(キャッシュフロー)が多くなることがあります。自己資金または融資を利用して購入するのか、出口戦略をどうするのかなど、総合的に検討する必要があるのが、不動産投資の難しさでもあり、醍醐味でもあります。
所得税・住民税
不動産収入(家賃収入等)は総合課税となり、給与所得などの所得と合算して計算します。累進課税となり、収入が高くなるほど税率が上がります。
【所得税・住民税の速算表 ※2021年5月現在】
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | 住民税 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 | 10% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 | 10% |
| 330万円超 695万円以下 |
20% |
427,500円 | 10% |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 | 10% |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | 10% |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | 10% |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | 10% |
建物評価が高い、または耐用年数が短い不動産の場合、減価償却費という実際には支払していない額を経費として多く計上できるため、節税効果が高くなるケースがあります。
〔減価償却費とは〕
経年とともに下落する「モノの劣化代」を、会計上の損失として計上できる経費を減価償却費といいます。※土地は劣化しないため、減価償却はしません。
PM費(プロパティマネジメント費用/入居者に係る費用)
以下の業務を委託するための、管理委託料と呼ばれる経費で、一般的に家賃総支払額の5%となります。(※物件や管理会社によって前後いたします。)
【管理委託料に含まれる主な内容】
・家賃・共益費・水道光熱費などの計算徴収
・賃借人の募集・審査・契約書の作成等
・賃借人の退去対応
・鍵の保管・交換
・賃借人のクレーム対応
・etc.
管理委託料の他に、入居付けした賃貸仲介業者に支払う広告料(家賃の1ヵ月以上)などが必要となります。
BM費(ビルメンテナンス費用/建物に係る費用)
建物の維持管理に必要な費用です。建物の規模や設備によってかかる費用が異なります。
【全てのアパート・マンションで必要なBM費】
・共用部等清掃費用
・消防設備点検費用
【該当する設備がある場合に必要なBM費】
・エレベーター保守点検費用
・受水槽清掃費用
・浄化槽保守点検・汲み取り費
・機械式駐車場保守点検費用
・etc.
例えば間取り(2LDK)と戸数(12戸)が同じ二つのマンションがあったとしても、設備の違いによって経費は大きく異なります。
【建物A(3階建・1フロア4戸・下水道)】
〔該当するBM費 ※概算額〕
・共用部清掃等費用 36万円/年(※3万円/月)
・消防設備点検費用 10万円/年
・受水槽清掃費用 8万円/年
合 計 54万円/年
【建物B(6階建・1フロア2戸・浄化槽)】
〔該当するBM費 ※概算額〕
・共用部清掃等費用 36万円/年(※3万円/月)
・消防設備点検費用 10万円/年
・受水槽清掃費用 8万円/年
・EV保守点検費用 48万円/年(※4万円/月)
・浄化槽費用 12万円/年(※保守点検2万円/年 汲取り10万円/年)
合 計 114万円/年
このように同規模の建物であっても設備によっては2倍近くの経費が必要となることもあります。どのような設備が設置されているかは必ず確認することをおすすめします。
水道光熱費
各居室で使用する水道光熱費は入居者が支払いますが、共用部の水道光熱費は家主が支払う必要があります。この水道光熱費も、先ほどのBM費と同様に設備によって金額が異なります。一般的にエレベーター、オートロック、水道増圧ポンプなどがあると電気代が高くなります。
修繕費用
建物を維持管理していくためのBM費用の他に、建物や各居室の修繕費用が必要となります。この修繕費用は建物の規模や設備によって異なります。
【主な修繕費用と実施目安時期】
・各居室の原状回復費用(入居者退去の都度)
・エアコン取替費用(11~15年目)
・給湯器取替費用(11~15年目)
・外壁塗装(11~18年目)
・屋根、屋上(塗装・補修11~15年目/防水・葺替21~25年目)
・EV大規模修繕費用(補修:15年目 交換:30年目)
・受水槽取替(25年目)
※実施目安時期は国土交通省作成の「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」及び「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に記載しております。
最後に
ランニングコストをそれぞれの項目ごとに確認していただくと、規模や設備によって大きな差が出てくることが分かります。ですので、収益不動産の購入検討をする際には、表面利回りなどの数字だけではなく、どのようなランニングコストがかかるのかを確認することはとても大切なことです。
当社、株式会社クルーズコーポレーションは、四半世紀以上にわたり不動産管理業を展開してきた株式会社クルーズより、仲介部門を独立させ2013年に設立しました。
仲介業務を主としながらも管理会社から生まれた会社として、お客さまに寄り添い、単に仲介だけでなく、さまざまなご要望にお応えすることを大切にしております。
今回、お伝えした不動産投資のランニングコストについても、管理会社から生まれた会社という特徴を活かし、しっかりとした調査・ご提案を心がけております。
収益不動産をお探しの際には、お気軽にお問い合わせください。